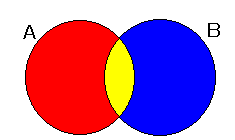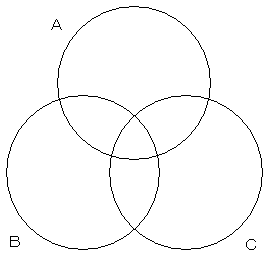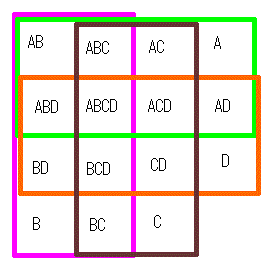| 定義
| 有限集合 A に対して,その要素の個数を n (A) と表す。
|
例えば,A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} のときは,n (A) = 10 です。
単位は不要です。
当たり前と言われればそれまでですが、次のことが成り立ちます。
| 性質
| 空集合 φ に対して,n (φ) = 0
全体集合 U の部分集合 A に対して,n (A) = n (U) ー n (A)
|
和集合の要素の個数について
2 つの有限集合 A,B に対して,n (A ∪ B) = n (A) + n (B) ー n (A ∩ B) が成り立つ。
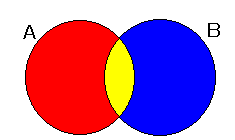
|
要素の個数の計算は,「すべての要素をちょうど 1 回ずつ」数えることが重要です。
共通部分が空集合でないとき,n (A) + n (B) を計算すると,共通部分を 2 度数えてしまいます。
このため、n (A ∩ B) を抜く必要が出ます。
共通部分が空集合であっても、上記の等式は成り立ちます。
| 例題 1
| 1 から 200 までの整数のうち,次のものの個数を求めよ。
(1) 2 の倍数
(2) 2 または 5 の倍数
(3) 2 の倍数でも 5 の倍数でもない整数
|
|---|
「1 から 200 まで」とは「1 以上 200 以下」のことです。
全体集合が 1 から始まるときは,全体を対象の数で割った商を求めるだけで構いません。
| (1) | 200 を 2 で割った商は 100 であるから,100 個
| | (2) |
1 以上 200 以下の 5 の倍数は 40 個
1 以上 200 以下の 10 の倍数は 20 個
以上より,100 + 40 - 20 = 120 (個)
| | (3) | (2)の補集合を指すので,ド・モルガンの法則より,
200 - 120 = 80 (個)
|
| 例題 2
| 100 から 200 までの整数のうち,次のものの個数を求めよ。
(1) 2 の倍数
(2) 2 または 5 の倍数
(3) 2 の倍数でも 5 の倍数でもない整数
|
|---|
100を含んで数えるので,全体は 101 個です。
確認ですが,例題 1 のうち,不要なものは「1 以上 99 以下」の整数なのです。(案外盲点のようです)
| (1) | 1 以上 99 以下の 2 の倍数は49 個あるから,100 - 49 = 51 (個)
| | (2) |
1 以上 99 以下の 5 の倍数は 19 個あるから,
100 以上 200 以下の 5 の倍数は,40 - 19 = 21 (個)
1 以上 99 以下の 10 の倍数は 9 個あるから,
100 以上 200 以下の 10 の倍数は,20 - 9 = 11 (個)
以上より,51 + 21 - 11 = 61 (個)
単純に例題 1 の (2) を 2 で割ってはいけません。
| | (3) | (2)の補集合を指すので,101 - 61 = 40 (個)
|
3 つの有限集合 A,B に対して,次の等式が成り立つ。
n (A ∪ B ∪ C) = n (A) + n (B) ー n (A ∩ B) ー n (B ∩ C) ー n (C ∩ A) + n (A ∩B ∩ C)
|
言葉で説明するよりも,下のスライドで理解した方が早そうな気がします…
どこから拾ってきたか、忘れてしまいましたが、4 つの集合のベン図も描けるようです。
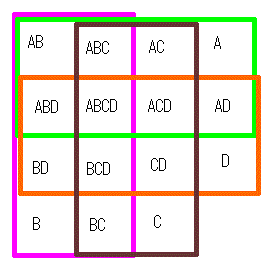
この図が参考になるかわかりませんが、共通部分が奇数個あるときは加える方向、
共通部分が偶数個あるときは減ずる方向になります。この法則を交代和と呼ぶことがあります。
|